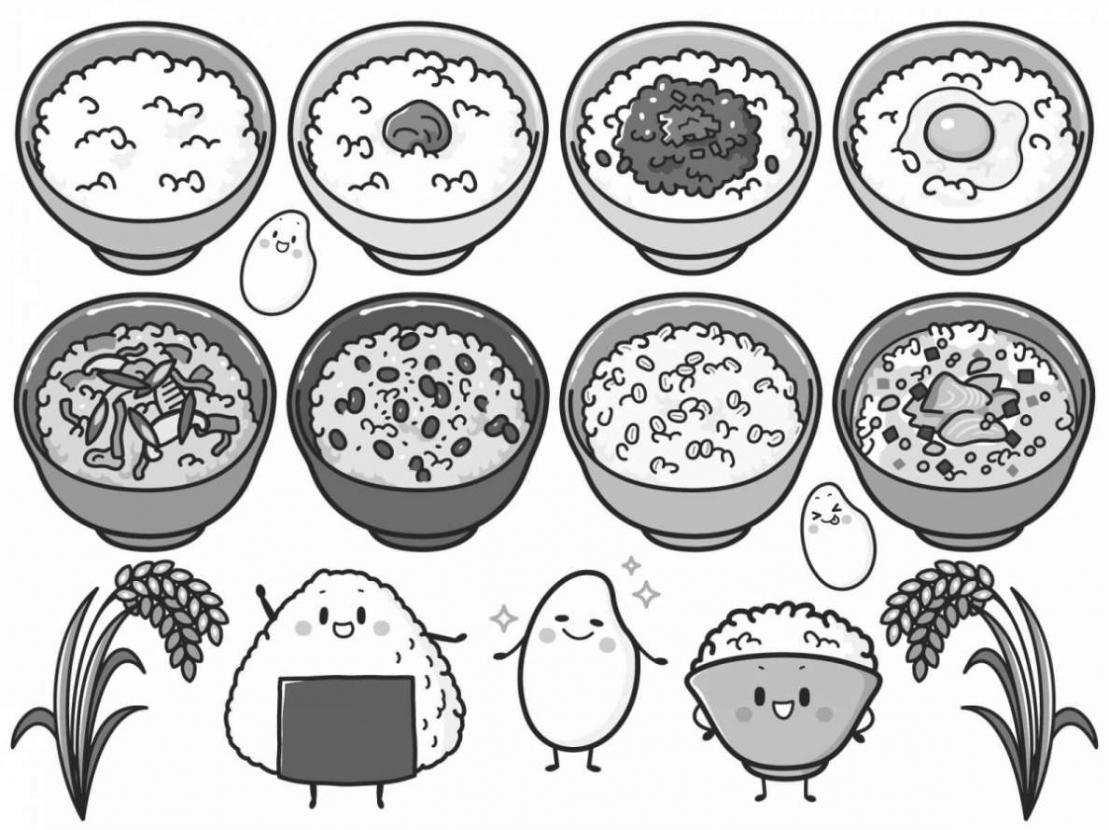
販売用の野菜や果樹の栽培において、害虫や疫病の発生は不可避的であり、防虫・防疫のための人為的な対策が欠かせません。市場に出回っている農作物のほとんどは、農薬を使用して栽培されたものです。農作物に残留する農薬は、人体や環境への悪影響が懸念されており、一定の規制が必要でしょう。
残留農薬を規制するため、どのような基準が設けられているのでしょうか?具体例として、IPMやコーデックスについて解説します。
農薬は何故必要なのか?
農作物の種類によって差があるものの、自然環境の下で栽培すれば、病害虫や雑草が発生して生育を妨げ、期待する収穫を得られないでしょう。除草・摘花・摘果といった農作業の負担も大変なものです。特に、田畑や温室で同一種の植物を集めて、同一条件の下栽培する現代農業は、害虫や病原菌の温床となるリスクを負わざるを得ません。
肥料や水がふんだんに補給される土壌では、雑草の成長も早いでしょう。こうした特徴は、高温多湿な気候の日本では顕著だと言えます。栄養が豊富で味が良く、実が大きくなるように品種改良された農作物は、野生の品種より害虫や病原菌に対する耐性も低いので、害虫や病原菌を駆除する人為的なメソッドが欠かせません。
病害虫や疫病を防ぐ方法として、農薬が最も効率的と言えます。農薬を使えば、除草・摘花・摘果などの負担も軽減できるでしょう。人体への影響が少なく農業従事者が使いやすい農薬が開発されており、農薬の種類や使用量を調節することによって、安定した防虫・防疫効果を得られます。
農薬の使用におけるリスク管理
農産物の生産に不可欠な農薬は、太陽光を浴び、水と混ざり、微生物により分解されることによって、時の経過とともにある程度減少するものの、どうしても一定量の農薬が農作物に残留してしまいます。残留農薬の量が健康に悪影響を与えない程度におさえるため、リスク管理が欠かせません。
日本では、残留農薬の生涯摂取量と1日ほどの短時間の摂取量の両方について、健康に害を及ぼさない上限を食品安全委員会が定めると同時に、厚生労働大臣が農薬の使用量に歯止めをかけるという二重の規制をかけています。
農薬使用量の制限については、作物ごとに基準が設定され、後述の国際基準に沿って安全性が担保されているのです。
日本の農薬使用率
農薬の使用量は、作物・雑草の種類のほか各国の気候や土壌条件などの違いによって、かなりの差があります。大豆・とうもろこし・小麦といったアメリカ等で生産量が多い農作物は、さほど農薬を使わなくても害虫の被害を受けることがありません。
しかし、果樹はどの国でも害虫が付きやすく、農薬使用量も多くなる傾向があります。水稲やジャガイモは、これらの中間くらいの使用量が必要になるでしょう。日本は、世界と比較すると温暖湿潤な気候の上、果樹や水稲の栽培量が多いため、農薬使用量がやや多量となる国に分類されます。
ただし、同一種の作物について農薬使用量を比べてみると、日本だけが突出して単位面積当たりの農薬使用量が多いというわけではありません。国によって農薬の使用量に一定の差があったとしても、適切な範囲内であり、決して過剰使用とは言えないでしょう。
農薬使用を規制するIPMという考え方
病害虫・雑草管理のため、農薬使用が欠かせないとしても、適正な使用が継続的に行われるよう規制が必要なことは言うまでもありません。実際に、戦後の経済復興と食糧難対策に専念した時代には、化学農薬に過剰に依存する農業が横行し、人間の健康を脅かす時期もありました。
また、特定の害虫を一掃する目的で使用された農薬が、益虫をも駆逐する結果を招き、逆に害虫の突発的大量発生の要因ともなったのです。同じ農薬を使い続けることにより、耐性を持った害虫が勢いを増すようになり、さらに強力な農薬を使わざるを得ないという悪循環も生まれました。
農薬規制につながる考え方として、IPMが挙げられます。IPMとは、Integrated Pest Managementのことで、「総合的有害生物管理」や「総合的病害虫・雑草管理」と訳されています。FAO(国連食糧農業機関)が定めたIPMの定義では、農作物に悪影響を及ぼす有害生物の制御に応用可能な全てのテクノロジーを総合的に組み合わせ、農薬使用が人体や環境に与えるリスクを低下させることとされています。
IPMでは、生態系への影響を極力おさえ、自然界に存在するシステムを利用して有害生物の発生を抑制し、安全な農作物を栽培することを目的としているのです。IPMを適正に活用すれば、農薬使用量を軽減できるでしょう。
ただし、IPMは農薬の完全不使用を提言しているわけではありません。IPMの特徴は、病害虫・雑草の発生をおさえるため、コストにかかわらずあらゆる方法を施すというわけではなく、経済的に許容できる範囲内で抑制するという点だと言えるでしょう。
コーデックスによる農薬規制
農薬規制を間接的に進めるIPMに加え、直接的に使用農薬を規制する国際基準が求められるようになりました。グローバリゼーションによって農産物が世界中に流通するようになり、食品・農産物・動物用飼料に残留する農薬について、 コーデックスMRLという国際基準が決められたのです。
MRLは、Maximum Residue Limitすなわち「残留基準値」を示します。コーデックスMRLは、世界保健機関(WHO)と国連食糧農業機関(FAO)が合同で運営している国際食品規格委員会により定められ、世界に発信されています。
この合同国際食品規格委員会は、コーデックス委員会とも呼ばれており、日本もコーデックス委員会の勧告に従って、残留農薬の規制を行っているのです。国によって残留農薬の規制基準が異なると、貿易において非関税障壁となるため、世界貿易機関(WTO)は、SPS協定(衛生植物検疫措置の適用に関する協定)を定めて、輸出物の統一的農薬規制をかけるようになりました。
そこで、WTO加入国の日本も、残留農薬の安全規制を国際基準に合わせるよう調整しなければならなくなったのです。コーデックスMRLは、動物実験によって得られた農薬の毒性を基準として、作物ごとに1日当たりの農薬摂取量を一定量におさえるよう設定されています。
このコーデックスMRLを、日本や欧米は農薬残留基準を設定する際の指標としているのです。
コーデックスを遵守する農法により担保される安全性

IPMやコーデックスの適用によって、農薬の使用量が規制され、消費者の健康が守られていると言えるでしょう。農作物を輸入する際にも、コーデックスのような国際安全基準を満たしたものであれば、安心して国内に供給できます。
ただし、農薬規制の基準が示されても、実際に個々のファームで遵守されなければ意味がありません。農水省といった公的機関による指導や出荷物の検査が不可欠です。